2024年10月、二子玉川 蔦屋家電にて、『パークナイズ:公園化する都市』刊行記念として、まちの保育園・こども園を営む松本理寿輝さんと馬場正尊のトークイベントが行われました。
トークテーマは「どんな都市の中で子どもは育ちたいか?」。まちの保育園・こども園での実践例を交えながら、地域に開かれた保育園運営や、子どもたちの創造性を育む教育の重要性が語られ、パークナイズとの共通項がいくつも見えてきました。今回のレポートでは、約2時間に及ぶトークイベントの中から、松本さんによるパークナイズの読み解きや、幼児教育の領域とパークナイズの共通項に関する話題をピックアップしてお届けします。
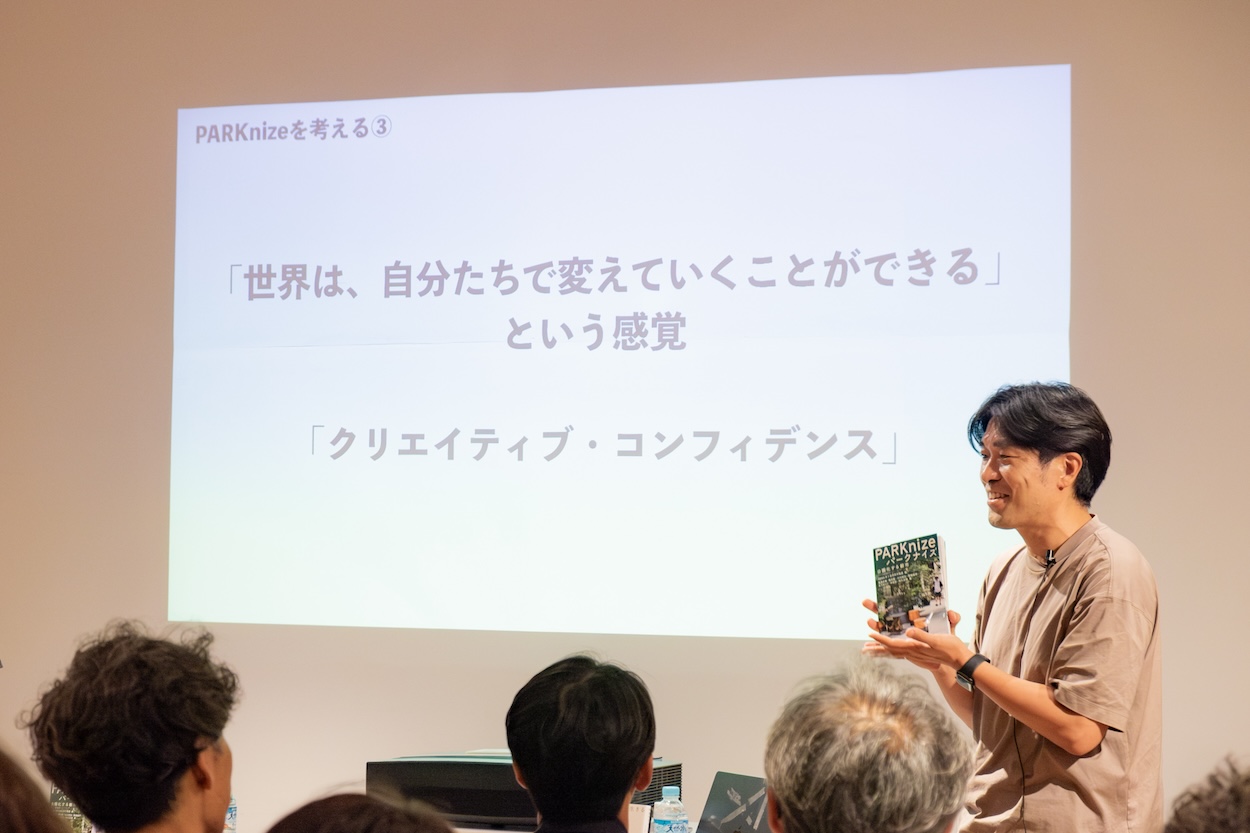
まちの保育園・こども園 代表/JIREA代表/まちの研究所株式会社代表取締役。1980年生まれ。一橋大学商学部卒業。博報堂、企業経営を経て、2011年「まちの保育園 小竹向原」を創設。現在、都内6拠点にて「まちの保育園・こども園」を運営。世界140カ国と学びのネットワークを形成するレッジョ・エミリア・アプローチの日本組織JIREAの代表も勤める。また、姉妹会社にまちの研究所株式会社(保育・教育・まちづくりのデザインコンサルティング会社)を持ち、子どもの環境を、自治体・企業・NPO・アーティスト・科学者等、あらゆる社会の主体と共創することを試みている。著書に『普通をずらして生きる:ニューロダイバーシティ入門』(リンクタイズ)など。
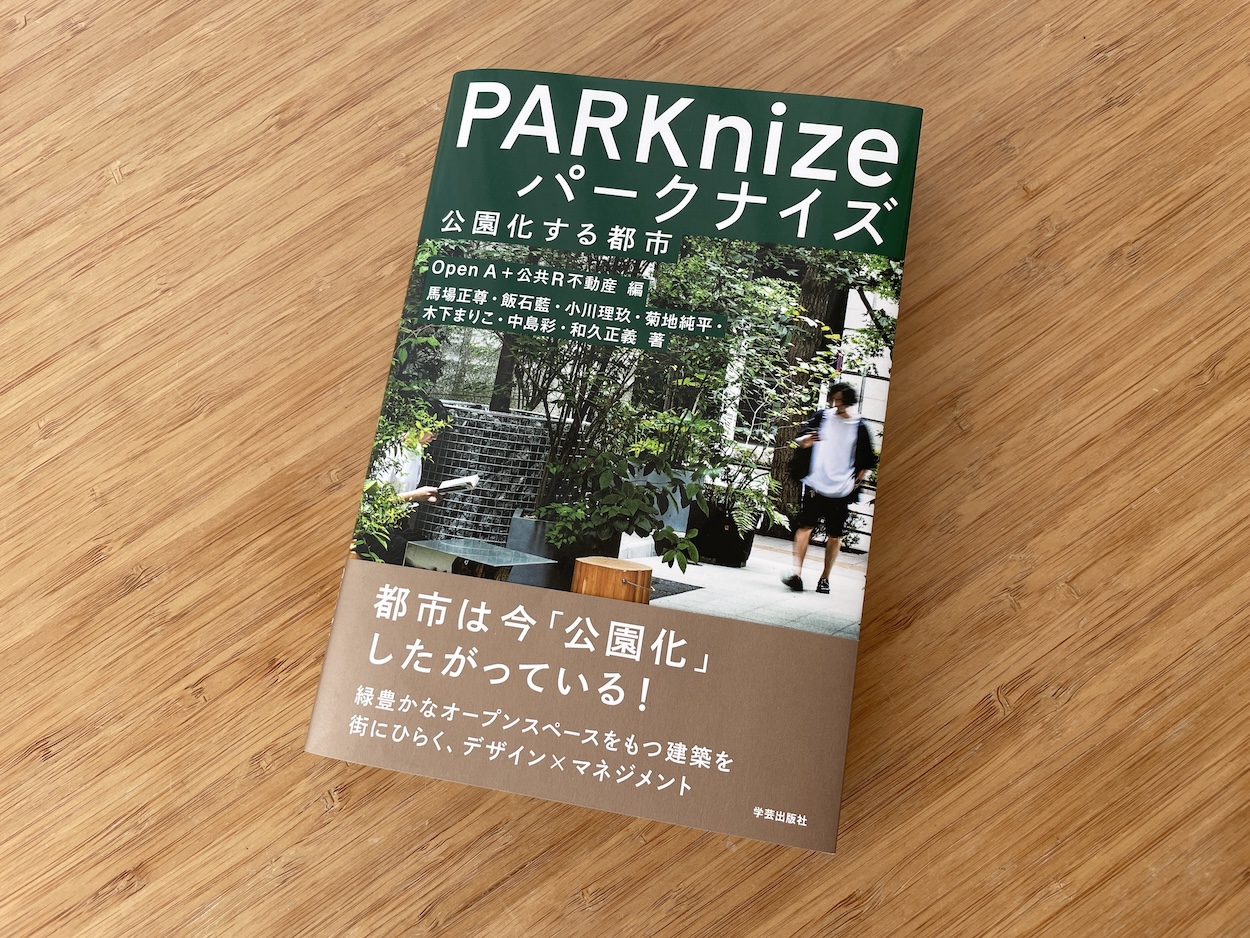
まちの保育園・こども園
幼児教育のフィールドで、実践と研究を行き来する
イベント前半では、パークナイズの本の紹介に続き、松本さんの活動についてご紹介いただきました。
現在、6つの拠点でまちの保育園・こども園を営んでおり、そのなかでも「こども園のパークナイズ」ともいえるのが「まちのこども園 代々木公園」。代々木公園の中に園があり、こども園として子どもたちの学び・育ちを支えることに加え、公園とつながりながら地域にも開かれた場として営まれています。
まちの保育園の立ち上げ当初から「子どもが育つ理想的な環境づくりとは、理想的な社会をつくることと同じなのではないか」と考えながら園をやっていたという松本さん。パークナイズの事例のなかに「コーディネーター」のような役割の人が登場しますが、まちの保育園・こども園にも似た役割の人がいるといいます。子どもたちの学びに地域の資源を活用し、また、保育園・こども園自身も地域福祉の拠点としても機能していけるよう、「コミュニティコーディネーター」という職種の人が、保育の枠を越えて人と人、人と地域をつなげるために、いろんな活動を行っているそうです。

まちの保育園・こども園と、その実践知をいかし社会との共創を図る「まちの研究所」では、「0から1をつくる」ことを大事にしながら、企業や自治体と一緒に新しい仕組みをつくっていく共創型のスタイルを大切にしています。まさに2024年10月時点で、石川県加賀市内の公立園にてまちぐるみの保育・教育を実践するための取り組みを、公共R不動産と一緒に進めていました。
ほかにも東京大学と一緒に乳幼児教育について研究したり、海外とも繋がりながらイタリア発祥の「レッジョ・エミリア・アプローチ」を実践したり、千葉工業大学学長の伊藤穰一さんと共にNPO法人を立ち上げ、従来の教育の枠にとらわれないインクルーシブな子どもたちの学びの場として「ニューロダイバーシティスクール・イン・東京」という学校も開設しています。実践で得た知見を社会に還元して、その循環の中で少しずつ経済も回しながら、また新しいチャレンジに投資して実践の内容をアップデートしていく。そんなふうに、まちの保育園・こども園を中心として、日々、実践と研究を行き来する活動が行われています。
まちの保育園・こども園の日々の現場についても紹介がありました。子どもたちがなにかを創作すると「自分たちのアイデアやイメージをもっと誰かに伝えたい」と、地域で展覧会などを開くこともあり、周りの大人や地域の人たちがどんどん巻き込まれていき、まち全体が盛り上がっていくそうです。
まちと子どもの関係について、松本さんがこのように話しているのが印象的でした。
「僕らが日々現場で実感してるのは、子どもとは、人と人をつなぐ理由になる存在だということ。子どもがまちに出ていくことで、地域にいるさまざまな人たちの『ウェルビーイング』にもつながっていく。まちには本当に多様な人が住んでいて、働いていて、子どもはその多様性を前向きに引き出してくれる“外的存在”だと感じることがあります。温度感のある、人と人との感情を伴うつながりが生まれていく。子どもたちの存在によって、地域そのものがもっと楽しく、心地よい場所になっていくと感じています」

パークナイズとまちの保育園・こども園
3つのキーワード
続いて、松本さんが見出した、幼児教育の領域と『パークナイズ』との共通項から、3つのキーワードを挙げていただきました。
1. エコトーン
自然界における「エコトーン(Ecotone)」という概念を起点に、社会や空間のあり方を見つめ直すことを提案した松本さん。エコトーンとは、「海と川の間」「草原と森林の境界」といった、2つの異なる生態系の狭間に位置する移行帯を指します。これらのエリアは、領域同士の中間的な空間であり、生物多様性が高く、なおかつ変革種といったイノベーションが生まれやすい場所。ところが、都市開発などの人工的介入によってこの中間帯が分断されると、両隣の生態系がバランスを崩すことがあります。エコトーンは生態系の豊かさを支えながら、新たな価値や関係性を生む基盤としても重要な役割を果たしているのです。
このエコトーンの概念は、都市や社会空間の設計にも応用できるのではないかと松本さんは話します。パークナイズの事例として、ストリートファニチャーを戦略的に「置く」ことによって、かつて硬直していた空間が、ふわりと開かれた「中間領域」として再構築されて、誰もが自然に立ち寄れるような場所へと変化したり、デパートの壁面を打ち抜いて空間を再編することで、本来の商業空間の境界がやわらいで、人々の交流や滞留が生まれたり。
「人間そのものがエコトーン的な存在としても機能している」という松本さん。集合住宅の「女将(おかみ)」や「公園長」のような存在が、人と場所の間に立ってやわらかく関係をつなぐことで、コミュニティの中に自然な共存や対話の場を生み出している。それは、まちの保育園・こども園で実践している「コミュニティコーディネーター」の存在もそれにあたるといいます。空間設計や運営の工夫によって、かつては断絶されていた都市の一部が、曖昧さを持つ「社会的エコトーン」として機能するようになるという考えです。


2. 「なる」主体性
教育の分野で研究が進められているという「主体性」という概念。松本さんは「する主体性」ではなく「なる主体性」の重要性に着目しました。「なる主体性」とは、行動を起こす前段階において、その人の内側に自然と湧き上がる「やってみたくなる」「その気になる」といった心の動きに基づいていること。単なる行動としての主体性ではなく、その前提となる内発的な動機に重きを置く考え方です。
「する」という主体性だけでは本質に迫れず、むしろ、「なんとなくやってみたくなった」という状態から自然と始まる行為こそが、自分にとって価値ある、本質的な主体性につながるといいます。その意味で、「なる主体性」は、好奇心や気分、予期しない気づきといった心の機微(きび)を捉えて、それをていねいに育てていくことが求められます。
パークナイズの書籍のなかで「なる主体性」を刺激するための環境づくりについて言及した松本さん。たとえば、「世界観をつくる」といったキーワードや、「当事者性」を引き出すような仕掛け、見た目に惹かれるベンチなど、思わず立ち寄ってみたくなるような空間のデザインは、人の心を動かして「その気にさせる」装置として機能しているという見解です。

3. 「自分たちで世界を変えていける」という感覚
「自分たちで世界を変えていけるという感覚」。ただし、ここで言う「世界」は、必ずしもグローバルな規模を指すものではなく、領域や文脈を限定しながら、自分がいま属しているコミュニティや場に当てはめられます。自らの関わりによってその場が変わったり、豊かになっていく手応えこそが、本質的に重要なのだということ。
この「変えられる感覚」は教育や学びの場にも通じるもので、自分の働きかけによって環境が変わっていく実感を持てることが、主体的な学びや関与を支える基盤となっていくといいます。

パークナイズの本で書かれていた、「竣工という概念を放棄して、運営者がつくり続けること」「『小さなマネジメント』によって手応えを持って場を動かしていくこと」、また「社会実験によって、変えていける感覚を体験すること」など、場づくりのプロセスの中で、人々が主体的に関わり続けられる仕組みについて言及した松本さん。こうした感覚が自分自身がなにかを生み出し、変化を起こせるという確信や自信につながっていると話します。

馬場 ありがとうございます。この3つのキーワード、すごくないですか。もうフィットすることだらけです。まず「エコトーン」という言葉、響きも含めてたまんない。
実は、パークナイズの本を書くときに「公園化する都市」じゃなくて「自然化する都市」という言葉も頭に浮びました。でもそれは少し早すぎると思った。なぜかというと、「自然化する都市」と言った瞬間に、人間がつくってきたインフラや造形物をちょっと否定するような感覚になって、建築をつくる人間として「自然化する」と言うわけにはいかないと。
人間が文化や建築とか、なにかをつくってしまう欲望と自然がそれを抑制しようとする中間にこそダイナミズムがあるし、クリエイティビティもある気がする。人間と自然がうまく調和しながら、調整しながら生まれているのが「公園」みたいな場所であって、まさにこのエコトーンという概念に近い。なにかとなにかの中間的な、いい感じの平衡状態ですよね。いまは公園が都市のなかに限定的にしかないのが、将来的にはばーっと広がっていくようなイメージがあります。
松本 たとえば、「存在」と「実在」という考え方があるのですが、「存在」として世の中のものをすべて科学的に見てしまうと、すごくドライで機能主義的になりすぎてしまうけど、「実在」のように「神さま」とか「ご縁」とか、「科学的に説明できないけど自分はあると信じていること」があると、生活や都市が少しおもしろくなっていく気がしています。エコトーンの領域は境界なので、お互いのことをあまり知り得てないから、可能性やイマジネーションでつながっていくしかない部分もある。そんなところが、ちょっとワクワクしたり、新しい創造につながっていく気がするんです。
馬場 僕は子どもと接するときって不思議な感覚になります。大人同士よりもダイレクトに反応が返ってくる独特の緊張感とか、ちょっと邂逅(かいこう)したときの嬉しさとか。実在の話もそうですよね。そういう感覚が大人になると少なくなってくるけど、エコトーン状態の2人との会話のモゾモゾした感じもすごい重要だったりするじゃない。曖昧な状態を僕らは考えたり、つくったりするべきだなと思いながら聞いていました。
松本 そういえば、本のなかで「見立てる」という言葉が使われていましたよね。実は保育の世界ではよく使われる言葉なんです。子どもたちは、積み木をスマホに見立てたり、積み木でまちをつくったりしますが、ただの遊びに見えて実は子どもにとってすごく大事なことなんですよ。
なぜかというと、1つはイマジネーション。想像力や発想力がすごく働いている。もう1つは、決まったルールがないなかで自由にやっていること。枠がないからこそ、自分で考えてどんどん展開していける。もう1つはそれを友達と一緒にやることで、イマジネーションがもっと広がって、遊びが楽しくなっていく。「想像力」「ルールがないこと」「友達とのやりとり」という3つの要素が「見立てる」という行為に詰まっているんです。

馬場 「する」じゃなくて「なる」という話もハッとしました。実は『エリアリノベーション』という本を書いたときに、「当事者化」という単語を思いついたんだけど、現場を見ていると、当事者化がちょっと重たそうで、疲れている人もいたりして。その場合はもしかしたら「する」主体だったのかもしれない。だけど「なる」っていうタイプの主体性は、自然だし、長続きするし、押し付けがましくない。すごく的確なキーワードだなと思ったんです。
松本 僕も「当事者性」はすごく大事だと思っていて、みんなが自分ごととして関わろうとする姿勢は本当に尊いなと感じます。その一方で、「弱いつながりの強さ」も大切な気がしていて。
あるコミュニティの中に深く関わる人たちがいる一方で、直接その中にはいないけど、外側からすごく心を砕いてくれる人がいる。その存在があるだけで、ちょっと疲れたときに息抜きができたり、別の視点に触れたり、場合によっては違うコミュニティに一時的にアクセスできたりするんですよね。そういう人が周辺をフラフラしていることが大切で、実は、コミュニティコーディネーターが担ってる役割でもあるんですよ。
馬場 まさにそうですよね。「弱いつながりの強さ」は、だんだん風景化していく気がする。弱いつながりって、やわらかいですよね。やわらかいから可変的。逆に、強くてガチッとしてるものは、実は柔軟性がなくて、なにかあったときに一気に崩れちゃったりする。
都市計画や建築も制度で固めてコントロールしようとすると、実は脆くなる。制度もマネジメントも「どれだけやわらかく保てるか」にかかってると思ってて。そんなやわらかさを支えてるのが、実はコミュニティコーディネーターのような存在なんですよね。臨機応変にその場に合わせて動ける、しなやかな職能を持った人たち。そういう役割を担う人材を育てていくことが、これからの都市計画や空間づくりにとって、めちゃくちゃ大事だと思ってます。
松本 教育とか学校領域でもコーディネーター人材の活用が注目されています。人々の当事者性をどう引き出して人と人を結びつけていくかが大切になっていきますよね。

馬場 最後に「自分たちで世界を変えていける」という言葉。「世界」を「まち」とも言い替えられると思うけど、この感覚をみんなに持ってほしいですよね。子どもたちをまちづくりとか都市デザインの当事者にする方法はないだろうか。カタチだけのイベントではなくて、しっかり実装につながるプログラムを組んでいく。公園やいろんな公共施設を設計して思うのが、子どもたちが生き生きと楽しそうな場所は、大人たちも間違いなく楽しそうだということ。逆に大人たちがかっこよくキメて盛り上がっている場所は、果たして子どもたちは楽しいだろうか?と思ったりもする。
松本 そうですよね。子どもとプロジェクトを組むっていうことですね。そこで大切なのは、子どもたちが答えを見つけるのではなくて、「いかに子どもたちによって、センスのいい問いが生み出されるか」だと思います。ワークショップでは大人が子どもに問いを渡しがちだと思いますが、そうではない。いい問いが見つけられれば、みんなで知恵を集めて、いい創造がしやすくなるはず。でもいい問いを見つけるのが、すごく難しい。
はじめに「このまちのどこにフォーカスして、なにを豊かにしたいか、なにをつくりたいか」という問いを子どもたちと考えていけると、おもしろいような気がします。
馬場 今度、子どもたちと一緒に、実際にやってみたいな。まちづくりとしてやってみたい。でも、子どもたちにいい問いを立てるための問いをどう出していいかわからなくて。ファシリテーションの方法も見てみたいです。
松本 むしろ馬場さんにも子どもたちと一緒にプロジェクトに参加してもらいたいです。
馬場 相当、通用しないんだろうな(笑)。
松本 これからも一緒にプロジェクトをやっていけるといいですね。
馬場 やっていきましょう。今日はありがとうございました!
2024年に出版された、松本さんと千葉工業大学の伊藤穰一さんによる共著『普通をずらして生きる ニューロダイバーシティ入門』(リンクタイズ)もぜひご覧ください。
https://amzn.asia/d/hJiZOIA

関連
PARKnize ─ 公園化する都市
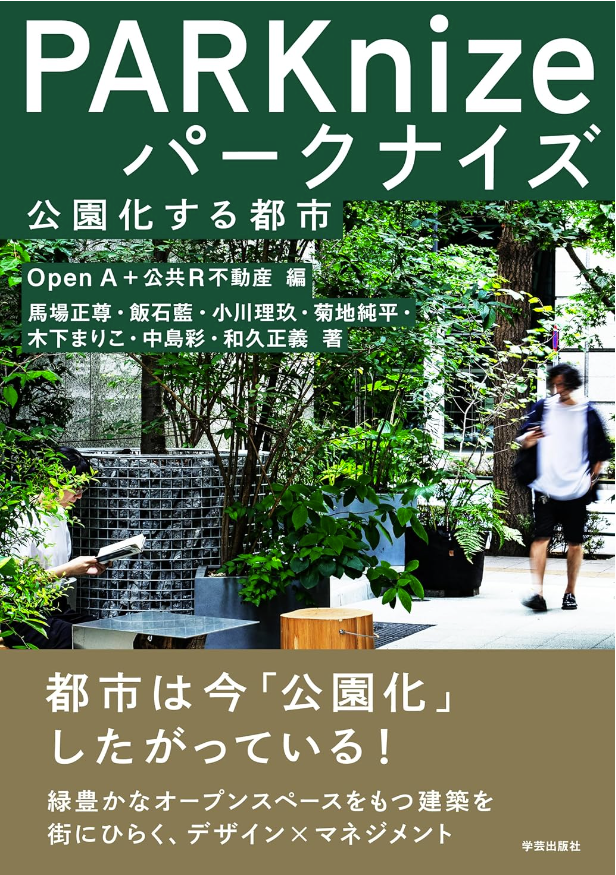
9月19日発売『パークナイズ 公園化する都市』(学芸出版)
テーマは「PARKnize=公園化」。今、人間は本能的に都市を再び緑に戻す方向へと向かっているのではないだろうか、という仮説のもと、多様化する公園のあり方や今後の都市空間について考えていく一冊です。
Amazonの購入はこちら
https://amzn.to/45PDUa3






