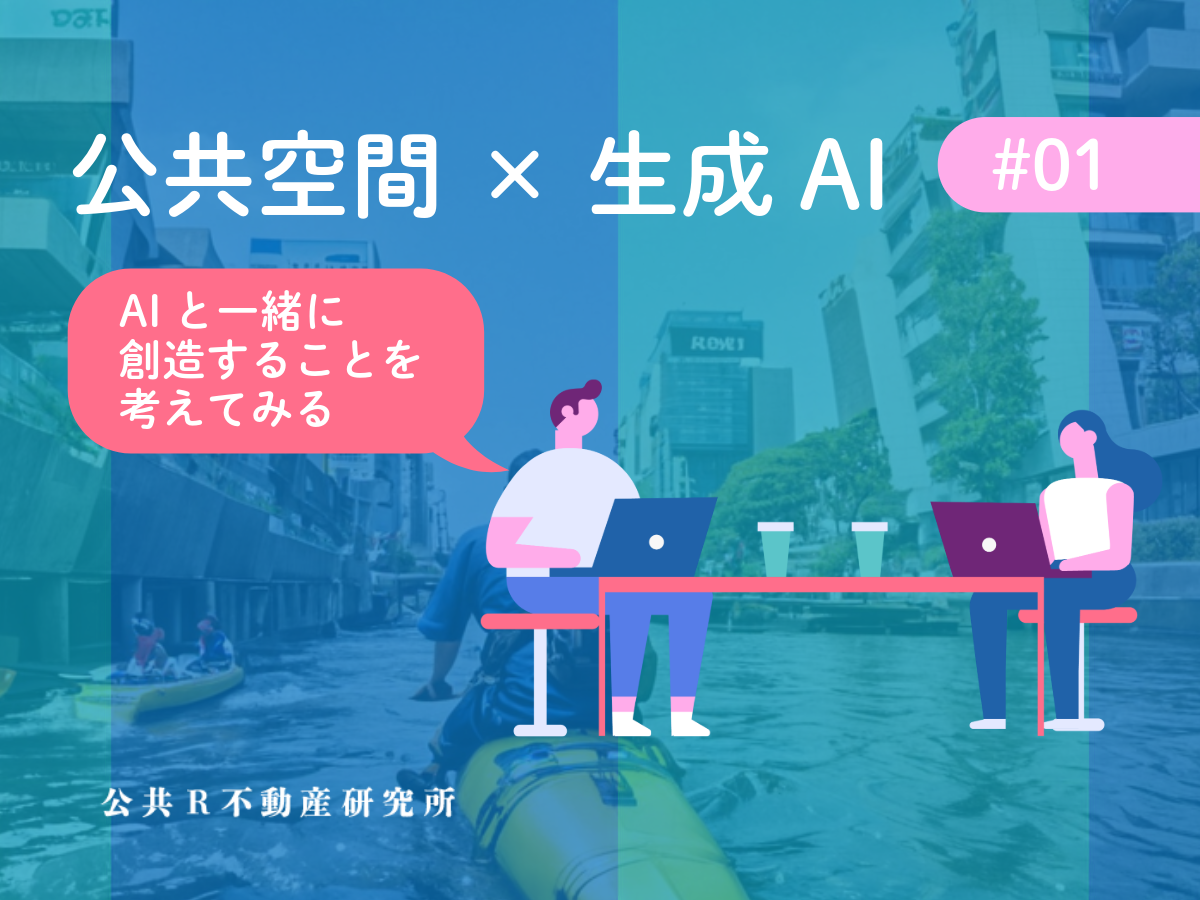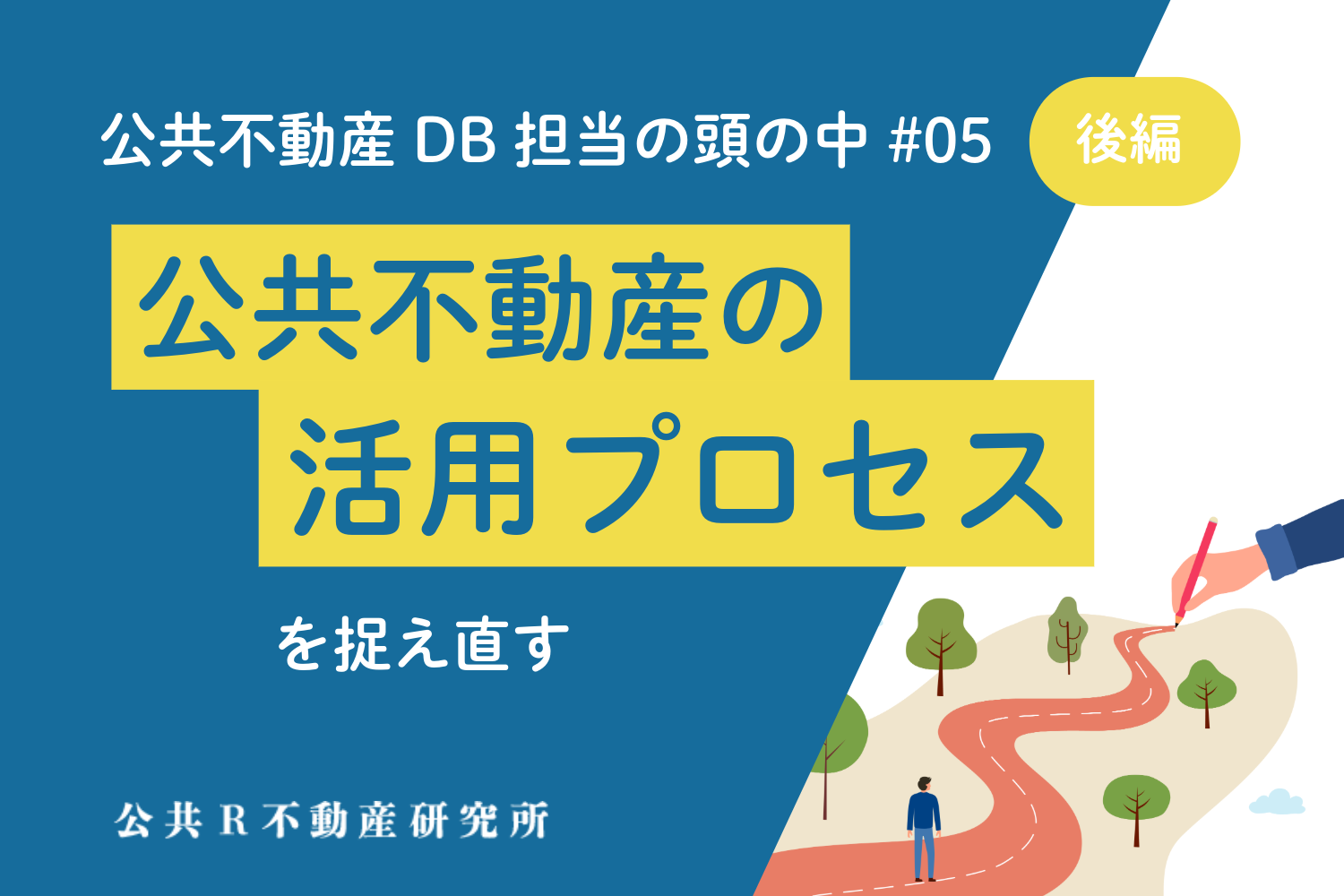連載
公共R不動産の本のご紹介
クリエイティブな公共発注のための『公募要項作成ガイドブック』
公共R不動産のウェブ連載『クリエイティブな公共発注を考えてみた by PPP妄想研究会』から、初のスピンオフ企画として制作された『公募要項作成ガイドブック』。その名の通り、遊休公共施設を活用するために、どんな発注をすればよいのか?公募要項の例文とともに、そのベースとなる考え方と、ポイント解説を盛り込みました。
自治体の皆さんには、このガイドブックを参照しながら公募要項を作成していただければ、日本中のどんなまちの遊休施設でも、おもしろい活用に向けての第一歩が踏み出せるはず!という期待のもと、妄想研究会メンバーもわくわくしながらこのガイドブックを世の中に送り出します。ぜひぜひ、ご活用ください!